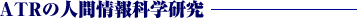



人間と機械

東京大学 先端科学技術研究センター 廣瀬 通孝
今日、情報技術の分野において、再び人間と機械とのかかわりが活発に論じられるようになってきた。モバイル・コンピューティング、ユビキタス・コンピューティングなど、新しいタイプの情報技術がつぎつぎと台頭し、新しいヒューマンインタフェース・パラダイムが要求されているからであろう。
「人間と機械」というテーマは、むかしからいろいろと議論されてきた息の長いテーマである。かなり性格の違う両者を接続しようというのだから、さまざまな問題が生じることは当然といえば当然であろう。人間という要素を科学技術に取り込もうとするとき、われわれがまず戸惑うのは、人間という対象がわれわれ自身だということである。自分自身を扱うということは、どこかで主観が紛れ込むことを意味する。科学技術においての基本は客観であり、本来主観という概念に対する方法論は存在しなかった。
主観とは、見える世界が個人々々で違うということを前提としている。であるから、そもそも皆違うのだというところから話を始めなければならない。科学技術は一般化が重要であるから、「同じ」ということが「違う」こと以上に大事である。したがって、われわれ科学技術者は、まず平均値を考えて、二次の微少量として個性を取り扱いがちである。ところが、個人々々のばらつきは平均値中心主義を超えるものがある。血液型を考えてみればよいだろう。A,
B, O, ABの4つのタイプがあって、この構造は平均的な血液型の周辺に分布しているわけではない。
要は平均値以上に分散が、「同じ」より「違う」が重要だということである。もちろんこれは困ったことばかりではない。人の指紋や眼底の血管像が皆すべて違うことは個人認証に役立てることができる。違うということをスタートとしてさまざまな新たな技術の応用可能性が見えてくるのである。メガネや衣類も一人ひとり違うという点から始まる技術である。工場出荷品のままでは用をなさず、個人にフィッティングするプロセスが不可欠で、それがメガネ技師やテーラーなどの新たな職能を生むことになる。今日、ウェアラブル・コンピュータが注目されているが、その本質的な新しさは、まさにそこにあるように思われる。このコンピュータではインタフェースが人間に密着して存在するために、個人の特性に極限までにチューニングできるし、そうでなければ本来の能力が発揮できない。個人間のシェア、貸し借りを前提としないということは、これまでのコンピュータとの大きな違いである。
ところでウェアラブル・コンピュータでもうひとつ面白いのは、それがまさに衣類としての特性も兼ね備えているという点である。これを身にまとうことによって、ユーザが外部からは機械に見えるときがある。たとえば、ウェアラブル・コンピュータが常にネットワークにつながっており、ユーザがそれを常に見られるとき、ユーザはネットワークからは端末に見えるだろう。ユーザの動作や感覚器からの入力を常に記録するウェアラブル・コンピュータを身につけると、大量のデータがたまっていく。その記憶はネットワークを介してアクセス可能である。これまでのヒューマン・インタフェースとは、生身の人間と機械環境との境界面を意味していたが、ウェアラブル・コンピュータの場合は、人間の側に機械が入り込んでいる。
誤解を恐れずに言えば、いかに機械を人間側に近づけることが出来るかという従来の哲学に加えて、人間を機械に近づけるというもうひとつの哲学が登場し始めているように思われる。ひとことでいえば、サイボーグの哲学である。一見これは荒唐無稽に見えるが、携帯電話を大部分の人々が身につけ、無意識のうちに例の親指インタフェースを駆使できるという状況は、人間にキーボードインタフェースが装着されたというようなものである。このような状況下では、高度なパターン認識技術によらずとも、はるかに実用的なインタフェースデザインが可能である。
このことは、人間と機械との境界面がゆらぎ始めていることを意味する。生身の人間と機械とは確かに対立概念である。ところが、人工知能技術の発展によって、いまや「機械的」という言葉の使用がためらわれるほど機械が人間化した。そしてさらに、今述べたような人間の機械化というような状況が顕在化してくると、両者の境界面のありかたは大きく変わってくるだろう。異質なものの二項対立よりは、もっとずっと重層的な関係になってくるのである。いま、人間と機械、ヒューマン・インタフェースが面白い。




