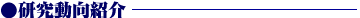



光衛星間通信
ATR光電波通信研究所 無線通信第一研究室 荒木 賢一
1.はじめに
宇宙を飛んでいる人工衛星の間で自由に通信ができれば、(1)衛星やロケットの位置と動きをより正確に把握できる、(2)通信衛星を利用する地上間の通信では必要な衛星や地球局の数を少なくできる、(3)いつでも地上と地球観測衛星や有人宇宙ステーションとの間で通信ができるなど、地上や宇宙での電気通信はもちろんのこと、これらを基盤とする宇宙開発も大きく進展します。このような衛星間通信は現在マイクロ波帯を用いたものが米国のデータ中継衛星TDRS(Tracking
and Data Relay Satellite)システムとして開発されています。将来に目を向けると、増える一方の衛星通信需要、宇宙飛翔体の増加、人類の宇宙への本格的な進出などに伴って、宇宙で扱うべき情報量は莫大なものになると予想され、これに対処できる新しい宇宙通信システムが期待されています。
ATR光電波通信研究所では、このような将来の宇宙通信を担う光衛星間通信技術の研究を行っています。衛星間の通信にレーザ光を用いることにより、装置の小型軽量化、通信容量の増大に加え相互干渉の無い通信が可能になります。しかしその実現には多くの要素技術の開発が必要となり、さらに国内はもとより国際間の研究協力が大切になります。当研究所では、我が国のポテンシャルを考慮にいれて図1に示すような要素技術を取上げ研究を進めています。ここでは、光衛星間通信で本質的に重要な光ビーム制御技術を中心に、その問題点、研究の概要などについて紹介します。
2.衛星間通信における光ビーム制御技術
光は波長が短いので、広がらないで非常に遠くまで届く光ビームを小さなアンテナで作ることができます。しかし、逆に広がらないことから衛星間を光で結ぶことが大変難しくなってきます。
一つの例として、静止軌道上に等間隔に配置した3個の静止衛星によるデータ中継システムを考えてみます。このとき隣どうしの距離は約74,000kmとなりますが、直径20cmのアンテナを使えば、波長0.85μmの光ビームの大きさを相手衛星の位置で約300mの直径にすることができ、数10mWのレーザ出力でも十分なデータ中継ができます。ところが、衛星の位置の誤差、姿勢測定誤差や姿勢の時間変化などによって、静止衛星では最大0.1度程度の方向誤差が見込まれます。これは相手衛星の位置に換算して考えると、相手が約260km四方の範囲(光ビームの800倍以上の大きさ)の何処かわからない所で揺れ動いていることに相当します。このため光通信回線を形成・保持するには、まず相手衛星を見つけ(捕捉)、相手を常に追跡しながら(追尾)、光ビームを送る(指向)という機能が必要になります。
このような機能を実現するための光ビーム制御装置の基本構成例を図2に示します。光アンテナ(高倍率の光学望遠鏡であり、これを光ビームの送受信両方に用います。)、送受信光学系、捕捉と追尾用の光センサ、信号処理回路、精追尾機構、光アンテナの向きやポイントアヘッド制御機構(光ビーム送信方向の微調を行う)を制御するオンボードコンピュータ等から構成されています。捕捉センサは0.2度から0.5度の広い視野を持つCCDイメージセンサであり、これによって相手衛星からのビーコン光あるいは信号光の到来方向を検出し、光アンテナの指向方向を制御し、受信光ビームを追尾センサ上に導きます。追尾センサには高感度の4象限APD(アバランシェフォトダイオード)を用い、このセンサの4つのエレメント出力に基づいて精追尾機構を制御して追尾状態を保持し、受信光を常に光信号検出器に導くとともに、送信光ビームを相手衛星の方向に正確に指向させます。送信光ビームは、受信方向ではなく光の往復時間内での衛星移動を考慮に入れた方向に送出されます。(光といえども有限の速度であるためこの補正が必要となります。ちなみに7万kmを往復すると約0.5秒かかります。)これは見込み角(Point
Ahead Angle)補正と呼ばれ、その大きさは静止衛星一周回衛星間の場合、通信用ビーム幅の数倍以上にもなることがあります。
小型・軽量で光の特長を最大限に活かした衛星間通信を実現するためには、光アンテナを始めとする光ビーム制御装置の構成要素、捕捉追尾方式に関して多くの研究が必要です。高精度の光ビーム計測技術、地上での捕捉追尾方式の実験評価、光センサの改良や評価、宇宙環境下での使用に耐える送受信光学系構成と信頼性の評価など問題は山積しています。当研究所では現在光ビーム制御技術に関して、(1)光アンテナと送受信光学系、(2)空間捕捉方式、(3)相互追尾と光ビーム指向のように課題を分類設定し研究に取り組んでいます。以下に、研究内容で代表的なものの幾つかについて紹介します。
(1)カセグレン型反射望遠鏡に代表される光アンテナは、送信光ビームの形成と指向、信号光の集光に使われます。これについては、光アンテナから出た直後の光ビームからビームの方向、ビーム幅を精度良く計測し、また制御する技術の研究を進めています。送受信光学系では、太陽・地球・月などからの背景光による雑音を低減するための光フィルタが重要な要素の一つです。半導体レーザの直接変調特性を考慮に入れた新しいものとして、背景光だけを有効に制限しうる光フィルタを考案し検討を行っています[1]。
(2)これまで考えられている光衛星間通信システムでは通常、捕捉を速く確実に行うために通信用光源とは別に捕捉用の大出力光源を備えています。しかし、システムの最終的な信頼性の確保と向上を考えると、通信用光源だけを用いる捕捉の機能も重要となるので、このような方式について検討を進めています[2]。
(3)指向・追尾の精度は熱による軸ずれ、機械的振動、追尾センサ雑音等に依存しています。また、当然のことながら相手衛星から到来する光の強度、即ち相手衛星における指向・追尾の精度にも依存しています。従って指向・追尾の過程で互いに影響を及ぼし合うことになり、悪くすると自分の誤差が相手の誤差を大きくしてしまう悪循環が生じ、追尾が外れ、回線断になります。このような衛星間の相互作用について検討した結果を図3に示しています[3]。安定した回線を保持するために必要な光ビーム幅と雑音等価角に対する条件を示していますが、この結果は追尾装置の軸ずれ量、雑音等価角に関する許容値を明らかにしており、衛星間通信システムの設計指針を与えるので重要です。
また、太陽のように強力な背景光があっても、双方向通信を行いながら回線維持力が可能な追尾方式を新しく提案し、その追尾特性や装置化等の検討を進めています[4]。
3.光変復調方式
光ビーム制御技術は光変復調方式も関係します。現在のところ、光衛星間通信に用いる光変復調方式としては光のエネルギーの強弱により通信を行う強度変調/直接検波方式が最も実現性の高い方式ですが、これには高出力半導体レーザの高速変調を必要とします。しかし、変調時の遠方界パターン等詳細はまだ十分に検討されておらず、送信光ビームの方向、ビーム幅に与える影響を評価していく必要があります。また、無線通信のように光の位相や周波数により通信を行うコヒーレント通信方式の場合、強度変調/直接検波方式に比べて受信感度が大幅に改善されるもの、衛星間通信特有の課題として光ビーム制御とも密接に関連する信号光と局発光の電界整合[5]、衛星の高速移動に起因する10GHz程度のドップラ周波数シフト補償などの問題があり、これらについても積極的に取り組んでいます。
4.内外における光衛星間通信の開発計画
光衛星間通信技術開発の動向としては、より小型高性能で信頼性の高いシステムを開発するため、現在高出力化と高性能化が進められている半導体レーザや固体レーザを用いたシステムについて、1990年代前半における宇宙実験の実現を目指しています。
米国では、NASAとMIT(マサチューセッツ工科大学)の共同で半導体レーザ(波長0.83μm)による、ACTS衛星(1991年打ち上げ予定)での実験が計画されています。INTELSATとCOMSATは半導体レーザを使った静止衛星間の短距離通信及び長距離中継回線の構想を持っています。この外、NASAとジェット推進研究所(JPL)は金星や火星等の惑星探査、さらには太陽系外空間の探査で、固体レーザによる光通信の計画を推進させています。また、1990年代に建造が予定されている有人宇宙基地では、静止衛星へのデータ伝送、実験機や軌道連絡船との通信等に光を利用することが考えられています。
欧州でも欧州宇宙機関(ESA)を中心に研究が進んでおり、1994年/1995年に仏の地球観測衛星SPOT-4と静止軌道上のデータ中継衛星間での通信実験が計画されています。
日本では、郵政省通信総合研究所(旧電波研究所)によって技術試験衛星ETS-VI(1992年打ち上げ予定)を利用した光衛星間通信の基礎実験が行われることになっており、またEDRTS(1994年打ち上げ予定)、静止プラットフォーム(1996年打ち上げ予定)においても光衛星間通信装置の搭載が考えられています。国内のレーザ応用技術、光通信技術、光デバイス技術及び半導体技術など関連基礎技術のレベルの高さから、日本における技術開発は国際的にも注目されています[6]。
5.おわりに
小型・軽量の装置で大容量通信ができるという光の特長が宇宙応用ではまだ十分に活かされていないようです。半導体レーザや固体レーザの高出力化と高信頼度化はアンテナを含め全体システムの小型化に繋がりますが、この外にも光ビーム制御系、通信方式の工夫などによって光の特長を本当に引き出した光衛星間通信を実現できると考えられます。当研究所では、このような光衛星間通信システムの実証モデル作製に向けた要素技術の研究を進めています。
参考文献


