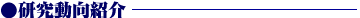



将来のディジタル移動通信に向けた多重波伝搬の研究

ATR光電波通信研究所 無線通信第2研究室 小川 英一
1.はじめに
自動車電話に代表される移動通信はめざましく発展していますが、今後はファックスやデータ等多種・多様なサービスに対応するために通信のディジタル化が必然的な動向です。更に、移動通信の特長を生かして、いつでも、どこでも、だれとでも通信できるシステムの実現をめざして研究が進められています。
移動通信はこのような将来性を持っていますが、その実用化は地上のマイクロ波通信や衛星通信等の固定した局間の無線通信システムに比べて遅れていました。この原因は一言で言うと移動通信の電波伝搬路の性質が他に比べて複雑で、これによる信号の劣化が著しいためです。自動車電話や屋内通信では周囲の建物群や壁面等からの電波の反射・散乱が生じて多数の波が重なって受信されます。この様な多重波の伝搬路では電波が互いに干渉し合うため場所により受信強度が激しく変化し、この中を移動しながら通信するため時間的にも非常に複雑に変動します。このことは、例えばタクシーに取り付けられたテレビ画面が走行中に激しく乱れること等で経験されます。更に、ディジタル通信では受信強度の他にも伝搬特性の問題点が生じます。
移動通信の歴史はこのような劣悪な電波伝搬の状態のもとでも良質な通信を可能とするための技術開発の歴史であり、今後、通信方式が高度になるにつれ益々この様な技術が重要になってきます。ATRでは将来の高速・広帯域な移動通信の実現をめざして研究を進めています。ここでは移動通信技術開発の基本となる電波伝搬の特性解明の研究について紹介します。
2.電波伝搬特性の複雑さ
多重波伝搬路での受信信号の強度は場所的、時間的に大きく変化し、例えば図1に示す様に1万倍も変化することがあります。現在のアナログ通信では信号が占有する周波数帯域幅が狭いため主に受信強度が問題になります。従って、従来の移動通信の伝搬特性では受信強度が距離や場所によりどの様に変化するかが研究されてきました。この場合には送信電力を大きくする等の手段で受信強度を改善することにより解決できます。
一方、ディジタル通信ではパルス波形をひずみなく伝送するために広い周波数帯域幅が必要になり、より高速度な通信にはより広い帯域幅が要求されます。このような条件ではアナログ通信の場合とは異なった伝搬特性の問題が生じます。ディジタル信号の伝送品質は符号誤り率(送信した符号のうち誤って受信される符号の割合)で表されます。図2に示す様に、多重波伝搬路では異なる経路から同じ信号列が到来し、通路長の差によって各々時間がずれて受信されます。受信波形はこれらが合成されたものですが、正規の符号時間点とは異なる時間点にも重なるために波形がひずみ、その時間位置での符号に誤りが生じます。この誤りの原因は、正規の到来波よりも遅れて到来する波(遅延波)による干渉で生じるため伝搬遅延ひずみと呼ばれます。この場合には、いくら送信電力を大きくしてもそれに比例して遅延波の電力も大きくなるため誤り率を改善することができません。この様に、高速なディジタル通信では伝搬遅延ひずみが伝送品質を劣化させる主な原因になります。遅延ひずみを克服する手段として信号処理技術やダイバーシチ技術(複数のアンテナを用い、そのうち受信状態が良いものを選択または合成して受信する技術)がありますが、これらの研究にも伝搬遅延ひずみの性質を明らかにすることが基本的な問題です。
3.多重波伝搬のメカニズム解明に向けて
遅延ひずみは電波伝搬路の多重波によって生じるため、到来する波の数や方向、受信強度や遅延時間差等、電波伝搬のメカニズムを解明する必要があります。ATRでは実際の伝搬路における特性を把握するため伝搬遅延測定装置を開発しました。ここでは、測定法の原理や、これにより得られた特性について述べます。
(1)遅延波形の測定
多重波の伝搬特性を解明するためには多重波を到来方向別に遅延時間とその強度を知る必要があります。到来方向は鋭いビーム幅をもつアンテナで分離できます。一方、遅延時間差を分解するためには、(1)レーダーのように鋭いパルスを用いる方法、(2)周波数に対する受信強度の変化からフーリエ変換により時間変化波形を求める方法、(3)決まった符号列を送信し、受信側で発生した同じ符号列との比較によって時間差を検出する方法[1]、があります。ATRでは微弱な電波で測定でき精度が良い(3)の方法を採用しました[2]。
この方法ではPN信号と呼ばれる疑似ランダムなパルス符号列を一定の長さだけ繰り返し送信します。受信側でも同じPN信号を発生し、これと受信波形とを比較して時間ずれを測定します。送信と受信とでPN信号を同期させるため、双方に非常に安定度の高い標準信号発振器を持っています。PN信号の特長は時間差の分解能が高いことです。時間ずれのある2つのPN信号列を比べる場合、時間が一致した時は相関係数(2つの波形の相似度を示す係数)が最大となりますが、少しでも時間がずれると急激に小さくなるからです。遅延時間の分解能はPN信号の周波数で決まります。開発した装置は周波数30MHzで約33nsecの時間分解能(10mの距離分解能)をもっています。これはトップレベルの性能で、将来の高速ディジタル通信や伝搬距離が比較的短い屋内における伝搬特性の解明に非常に有効な測定装置です。
図3で遅延時間測定の原理を説明します。図の様に、直接波と時間遅れがある反射波の2波の合成により受信波が構成されている場合を考えます。受信側でも送信側と同じPN信号を発生しますが、その周波数を送信側よりもわずかに低くします。従って、受信側のPN信号は送信信号に比べて少しづつ遅れた波形となります。相関器で両波形の相関を検出すると、まず、直接波が到来する時間点で相関が大きく出力されます。受信側で発生するPN信号が時間的に遅れるので波形の相関は徐々に小さくなっていきます。次に、PN信号の時間ずれが反射波の遅延時間点まで大きくなると再び相関が大きくなります。この様に受信PN信号の時間をずらせることにより遅延波形の時間軸が拡大され、精度良く時間差を測定することができます。
(2)屋内における多重波の伝搬
実際の伝搬路で多重波の到来特性を調べるため、全周方向から反射波が受信されて波形が大きくひずむことが予想される屋内において遅延波形を測定しました。図4は送、受信とも水平面内無指向性のアンテナを用いた場合の遅延波形です。反射等による遅延波がなく直接波のみの場合には、図中の破線で示す単峰の波形が受信されます。しかし、周囲から種々の遅延時間と強度成分をもつ多重波が合成されるため、図の様に複数の山をもち、さらに、山の幅も拡がります。300nsecを越える遅延波も存在していますが、これは伝搬距離で100m程度になります。測定した部屋の長辺は約15mですから3往復(壁面で6回反射)する多重反射波が存在することが分かりました。遅延波形の2つめの山は最初の山から約100nsec遅延しています。例えば、10Mbpsの伝送速度では符号間の時間間隔は100nsecになり、2つめの山は次の符号の時間点に干渉して誤りを生じさせる原因となります。この様にディジタル通信では遅延波形の拡がりが符号誤り率を劣化させる大きな問題点となります。
図5は図4と同じ伝搬路において、受信側に鋭い指向性(ビーム幅14°)のアンテナを使用し、到来方向を区別して測定した全周方向の遅延波形です。手前0°方向が送信点に正対しています。大きな遅延が生じている230°の方向は金属パネル壁の方向で、ここでは10回以上多重反射していることが推測できます。全方向からの波を同時に受信した図4の波形と比べて、遅延波形の拡がりは到来方向によって増加や減少があり、大きく変化することが分かりました。
上で述べた様に、符号誤り率は遅延波形の拡がりにより劣化します。遅延拡がりの小さい伝搬路条件が得られれば伝送品質を改善できます。ある方向では遅延拡がりが小さくなることを利用する改善技術として、前述のダイバーシチ技術の1つである指向性ダイバーシチがあります。その構成は図6に示す様に、複数のアンテナを全周方向に向けて配置し、これらのアンテナ出力のうちから遅延拡がりの小さいものを選択して受信します。
遅延拡がりの改善効果は使用するアンテナのビーム幅に依存します。図7は種々のビーム幅に対する遅延拡がり(遅延時間平均値の周りの標準偏差)の変化を調べたものです[3]。ビーム幅14°の値は図5の実測値で、その他のビーム幅についてはこれらの実測値から指向性の差によって重み付けして計算した値です。遅延拡がりの分布は到来方向に対する変化を表しています。指向性ダイバーシチによる改善効果は遅延拡がりの最小値で評価されます。実線は幾何光学的な多重反射を仮定して計算した最小値で、実測値と良く合っています。無指向性アンテナに比べて、例えば90°以上のビーム幅では遅延拡がりは余り改善されませんが、45°以下にすれば1/2以下に改善できることが分かりました。この様に、伝搬特性を解明することにより、その対策技術も明らかにできることが期待できます。
4.むすび
移動通信技術の基本となる電波伝搬特性についてATRでの研究を紹介しました。電波伝搬のメカニズムを明らかにすることにより方式の設計に必要な伝搬モデルを確立することが今後の課題です。移動通信では電波伝搬・アンテナ・通信方式のそれぞれの問題点が不可分であるため、互いに関連させて研究を進めています。
参考文献




