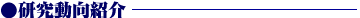



RとL、あなたはききとれますか?

ATR視聴覚機構研究所 聴覚研究所 山田 玲子
現ATR人間通信情報通信研究所
無響室(外部の音を遮断し、内部の音の残響がつかないように作られた特殊な実験室)の中でマイクに向かってしゃべるみなちゃんの声が外のモニター室に流れている。みなちゃん(6才)は、両親のアメリカ赴任に伴う1年間のアメリカ生活を終えて帰国したばかり。
「1から10まで数えてください(実験者)。」
「ワン、ツー、スリー」
かなり日本人的な発音だ。やはり、1年程度の滞在では、英語の音を獲得するには不十分なのだろうか。
「今度は曜日の名前を言って下さい(実験者)。」
「Sunday, Monday, Tuesday」
これは全く日本人離れした流暢な発音である。日本人が苦手とするRとLの聞き取りテストの結果もほとんどアメリカ人と同じ結果であった。1年間のアメリカ滞在経験と日本語化された英語の経験がともにみなちゃんの英語の発音、知覚に影響を及ぼしているようだ。
1.はじめに
行動や心的機能の発現について、それが遺伝による生得的なものか環境による獲得的なものかという2分法的な問題設定は、繰り返し用いられてきました。しかし、いうまでもなくどちらか一方の要因によって発現する形質や機能は少なく、多くのものは両者の交互作用により形成されます。したがって、両者それぞれの役割や相互の関係を理解していかなければなりません。
鳥に例をとってみましょう。アメリカにミヤマシトドという鳥がいます。この鳥は地域によってさえずりに特徴がある、つまり方言があるということで有名です。種を特徴づけるさえずりが可能となるか、それがどの方言であったかは、ひなの時の環境(まわりの成鳥のさえずり)によります。これは明らかに環境の影響です。だからといって同じ地域に棲む他種のさえずりを覚えるわけでもないし、学習可能な時期(敏感期)も限定されています。これは、生得的に決定された特徴です。さえずりの種類はそのときどきの環境から取り込まれますが、学習能力そのものは生得的なものです。
ところで、一般に私達は人間である以上みんな同じように見たり聴いたりするという前提に立っていないでしょうか。しかし、言語環境の違いにより、言語音の知覚すら異なります。この言語音の知覚の違いは、本格的な国際化時代を迎えた日本人にとって、異なる言語を使用する人々とのコミュニケーションを図る上で非常に切実な問題のひとつとなっています。例えば、多くの言語にあって日本語にはないRとLの区別がそうです。日本人がRとLの区別ができないというのは音声について研究する者の間では世界的に有名で、興味ある研究対象と考えられています。我々日本人にとっては、何故アメリカ人がRとLの区別ができるのか不思議であるし、アメリカ人にとってみれば何故日本人はそれらが区別できないのか不思議でしょう。
日本人はR、L音をどのように知覚しており、アメリカ人とどう違っているのでしょうか。また、アメリカに滞在する、つまり、米語環境にさらされることによって、どのように変化するのでしょうか。これらは大変興味ある問題です。
2.RとLの音響的差異
図1はアメリカ人が発話した“right”“light”という音を音響分析した結果です。これは、サウンドスペクトログラムと呼ばれる図で、たて軸は周波数(単位はKHz)横軸は時間(秒)を示し、スペクトルの強度が濃淡で表されています。よく見ると、何本かの濃い帯が観察できますがこれはホルマントと呼ばれ、周波数の低いものから順にF1(第1ホルマント)、F2(第2ホルマント)、F3(第3ホルマント)と呼びます。図1では、“rai”および“lai”の部分のF1、F2、F3を白抜きの線で示しました。母音や一部の子音では、このホルマントのうち低い方の3つ、つまりF1、F2、F3の高さ及びその時間的な推移が、音韻を決定します。ところで、RとLの比較ですが、“right”,“light”という単語ではそれらの音が語の先頭にあるので、先頭の部分F1、F2、F3に着目してみましょう。すると、非常に大きい違いがあることがわかります。F3の周波数がRでは約1KHzと低いところから始まり、Lでは約2.8KHzと高いところから始まっています。また、F2周波数もRの方がLに比べて多少低いところから始まります。F1は、次の“ai”という音に向けて、RではLに比べてゆっくりと変化しています。これらの特徴には個人差もありますし、個人内でも変動があります。しかし、それらの変動を越えて、アメリカ人は共通の手掛かりを用いてR、Lを聞き取っています。
そこで計算機を用いて“right”、“light”という単語を合成してみました。その際上述の分析結果をもとに3つの特徴をRからLまで19段階に分けて変化させた音を合成してみました。つまり、Rらしい音、Lらしい音、そして物理的にはそれらの中間的な性質を持つ音を19個作りました。このような物理的には連続した性質をもつ刺激群を刺激連続体と呼びますが、このように物理的には等間隔につくられた子音の刺激系列を同定させる(何という音か答えさせる)とあるところを境に急に答えが変化します。しかも、刺激連続体上数ステップ離れた音同志の弁別能力(違いがわかるかどうか)を調べると、同定の答えにおける境界をまたがない刺激音同志(つまり同定結果が同じ音同志)よりも境界を横断する刺激同志(つまり違う音と同定した音同志)の方が違いがよくわかります。このような知覚は範疇的知覚と呼ばれています。本実験で用いた刺激連続体を約3分の2のアメリカ人はR、Lふたつの音の範疇に分けて知覚し、残りのアメリカ人は同じ連続体上の中間あたりの音をW(つまり“wite”)と聴いたため、結果は図2左のようになりました。しかしRとL、またはR、L、Wの境界付近で弁別率が上昇しており、総じてアメリカ人はRとLを範疇的に知覚するといえます。それに対して、日本人はRとL刺激連続体を範疇的に知覚しません(図2参照)。日本人では、R側の刺激からL側の刺激に向かうにつれて、Rという答えはだんだん減り、Lの答えが増加してきます。しかも、その途中にW(つまり“wite”)という音がきこえます。また、最もRらしい音でも100%Rと答えることはないし、Lについても同様です。弁別率も顕著なピークはみられません。
3.知覚の手掛かり
前々項でRとLを区別する3つの音響的特徴について述べました。アメリカ人はこれら複数の特徴をどのように用いてRとLを聴き分けているのでしょうか。日本人はどうでしょう。前項の実験では、3つの音響パラメータは同時にRからLまで変化させた刺激連続体を用いましたが、ここでは、F2周波数とF3周波数の種々の組み合せの音を合成し、F2~F3平面上での音をアメリカ人と日本人がどのように同定するかを調べました。すると、アメリカ人はF2周波数の値にかかわらず、F3が2KHz以下の刺激をR、2KHz以上の刺激をLと同定します(図3参照)。言い替えれば、F3を手掛かりにRとLを同定しているといえます。それに対し、日本人では、F2~F3平面上でのRとLの境界が軸に平行とならず、F2周波数、F3周波数をともに手掛かりとして用いており、しかもF2周波数に強く依存していることが明らかになりました。さらに、日本人の場合、F2周波数が低い領域にWが聴こえます。
5.米国滞在経験と年齢
日本語に存在しないR、L音知覚については、アメリカ人と日本人のそれは大変異なっていました。それでは、日本人でアメリカに滞在経験を持つ人は、どのようにR、L音を知覚するのでしょうか。家族でアメリカに赴任し、数年過ごした結果、子供だけが流暢に英語でコミュニケーションを行なうことができるようになった、しかも兄弟のうち年齢の若い方が早かったという話をよく耳にします。そこで、帰国子女を含む滞米経験のある日本人のR、L音知覚について調べました。
研究の対象としたのはアメリカに1年以上の滞在経験を持ち、しかも滞米期間中、週に5日以上通勤または通学(現地校のみ、日本人学校は除外)し、そこで英語を用いていた日本人約150名です。知覚実験の結果、滞在経験者のなかには、アメリカ人同様の知覚を獲得した被験者がいる一方、滞米経験が数年あっても日本人型の知覚を示した被験者もいました。ここで重要なのは滞米年齢との関係です。実験の結果は、滞米開始年齢が7才以上になると獲得できなくなる人が増えてきます。同程度の滞米年数をもつ被験者について結果をまとめると、知覚実験のスコアが滞在開始年齢が7才をこえるとだんだん低下します。
冒頭で例に挙げたみなちゃんは5才から1年間滞米、帰国直後に実験に参加してくれました。成績は、アメリカ人の同年齢の子供の結果と全く同じでした。そしてさらに1年半後、再び実験をしてくれました。1回目の実験と2回目の実験の間は特別な英語教育は何もしていないということですが、聞き取りの成績は全く落ちることはありませんでした。みなちゃんとは対照的なのが中学、高校生時代に1年間米国に留学経験をもつ方達の結果です。150名中、このケースの方が30名とたくさんいました。しかし、そのうちのほとんどの人が滞米経験をもたない日本人と変わらない成績を示し、米人に近い成績を示したのはわずか2名でした。
これらの結果はあたかも、音声を獲得するための臨界期があることを示唆するかのようにみえます。しかし、このような結果から性急に、人間の言語獲得には学習可能な臨界期あると結論すべきではありません。臨界期とはそれ自体そのメカニズムを分析すべき現象であって説明に用いられる概念ではありません。この現象には、音声知覚に関する学習能力の低下以外に種々の要因が関与していると考えられます。例えば、12才から始まる日本での英語教育を受けることより、英語に関する言語学的な知識を獲得しますが、このことは音の獲得には阻害的要因として働くかもしれません。我々大人は、アメリカ人が目の前で話しはじめた時、RとLを聴き分けようとどれほど努力しているでしょうか。多くの人は、RかLらしき音はとりあえず“日本語のラ行音”というひとつのカテゴリーに放り込み、文脈に頼ってRかLを判断しているのではないでしょうか。例えば、日本人は“rook”という語を聴くと非常に高い確率で“look”と聴こえたと答えます。逆に“led”という語は“red”と答えてしまいます。この現象は“ru”や“le”の部分だけを聴かせた場合には起こりません。これは日本人がRとLをききとるプロセスに単語の意味、親密度という文脈が影響している証拠です。つまり、知識が大きく関与しているといえます。日常会話においてRとLを聞き分けられない者が文脈を手掛かりに聞き分けること自体はR、Lの聞き分けを助けているのですから問題はないともいえますが、長い目でみた場合には文脈ばかりに依存することによって音声知覚そのものの学習を阻害している可能性は充分あります。また、第一言語との干渉や言語の機能の年齢にともなう変化等も学習結果を左右するひとつの要因であると思われます。もちろん生成(発音)との関係も重要な要因でしょう。単に学習能力の限界と考えず、これらの要因をさらに分析することにより、年齢の影響を打ち破る効果的な訓練方法が導かれるかもしれません。実際、滞米開始年齢が12才以降であっても滞在年数が長期に及ぶと獲得する可能性は増します。
6.今後の研究の展開
ATR視聴覚機構研究所では、人間の視聴覚のメカニズムに学んで優れたマンマシンインタフェース技術の開発に向けた要素技術の研究にとりくんでいますが、このうち本研究は人間が発達の過程において音声言語をいかに自然にかつ巧みに学習し、身につけていくかという課題にせまり、「音声を聞き取る」メカニズムを解明する糸口を与える重要な研究テーマと考えています。
人間がどのように各言語環境に適した音声知覚能力を学習するかという問題にアプローチする際、実験室で音声知覚の訓練を行ない、どのような訓練がどのように知覚に影響を及ぼしたかを調べる方法があります。将来、このようなアプローチをとることにより、さらにもう1歩学習のメカニズムの解明に近付くことができると考えられます。例えば前項では年齢の影響を滞米経験者の知覚を測定することによって調べましたが、滞米経験中にどのような生活をしていたかとか、英語でコミュニケーションしていた頻度等は当然統制しきれません。さらに詳細に学習の達成度と年齢の関係について調べるためには、研究室内での訓練成果を比べるより他に方法がありません。訓練の実験にあたって、まず訓練音声としてのどのような音声の集合が適当かという訓練音声の最適構造の解明の問題があります。また、この訓練音声の構造化の要因とは別に、音声学習にはもう1つの要因があります。それは「やる気」です。いくら教材がよくてもやる気がなくては学習の効果は期待できません。このやる気は、心理学では動機づけ(motivation)と呼ばれ、学習における重要な要因のひとつとして研究されてきました。特に年少者の訓練において動機づけの問題は、重要な位置を占めることになると思われます。
このような言語音の訓練の結果は、外国語音の獲得メカニズムを知るきっかけとなる他、外国語教育にも役立つと思われます。ここ当分、日本人のR、Lの出番が続くかも知れません。筆者自身もこの分野で力を尽くしたいと考えています。
7.おわりに
英語に対するコンプレックスを抱えている我々大人の悩みとは裏腹に、情報の国際化が進むにつれ、言語という環境の相違はどんどん薄れていくようです。正しい日本語がくずれていくのではという心配がある一方、コミュニケーションの円滑化ということでは喜ぶべきことでしょう。子供向けのテレビ番組をみていても、随分英語が取り入れられています。言語の違いをメシのタネにしている者としては、少々あせってしまう今日この頃です。
本稿でご紹介させていただきました研究概要のデモがMacintosh, Hyper Cardのスタックとして作成されています。このスタックでは、研究概要をご覧いただくとともに、みなさんのR、L音知覚のテストや訓練も行なえるようになっています。ご興味のある方は企画部までご連絡下さい。
*謝辞*
本研究をすすめるにあたりご協力いただきました学校法人千里国際学園、同志社国際中高等学校、同志社大学、同志社女子大学の諸先生方並びにスタッフの皆様、被験者としてご協力いただきました皆様に心より感謝いたします。
研究上の討論や大規模な実験の遂行に関しても多くの方々の支援を受けました。ここに記し、心より感謝いたします。




